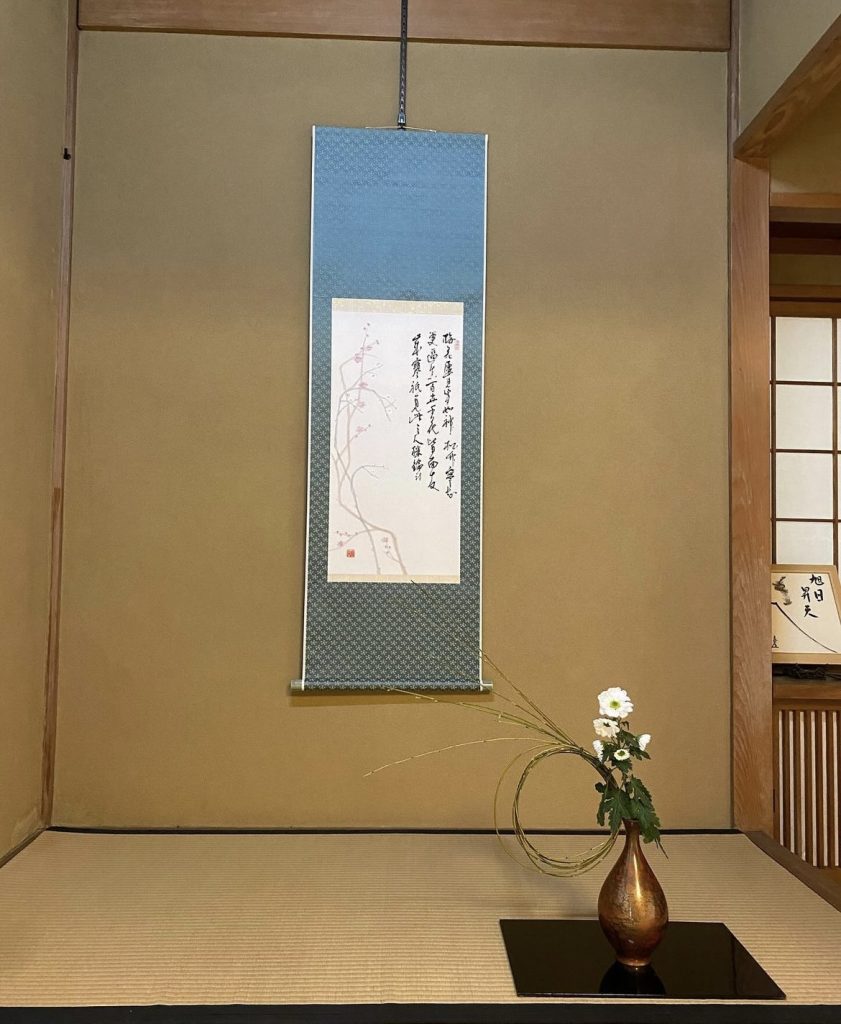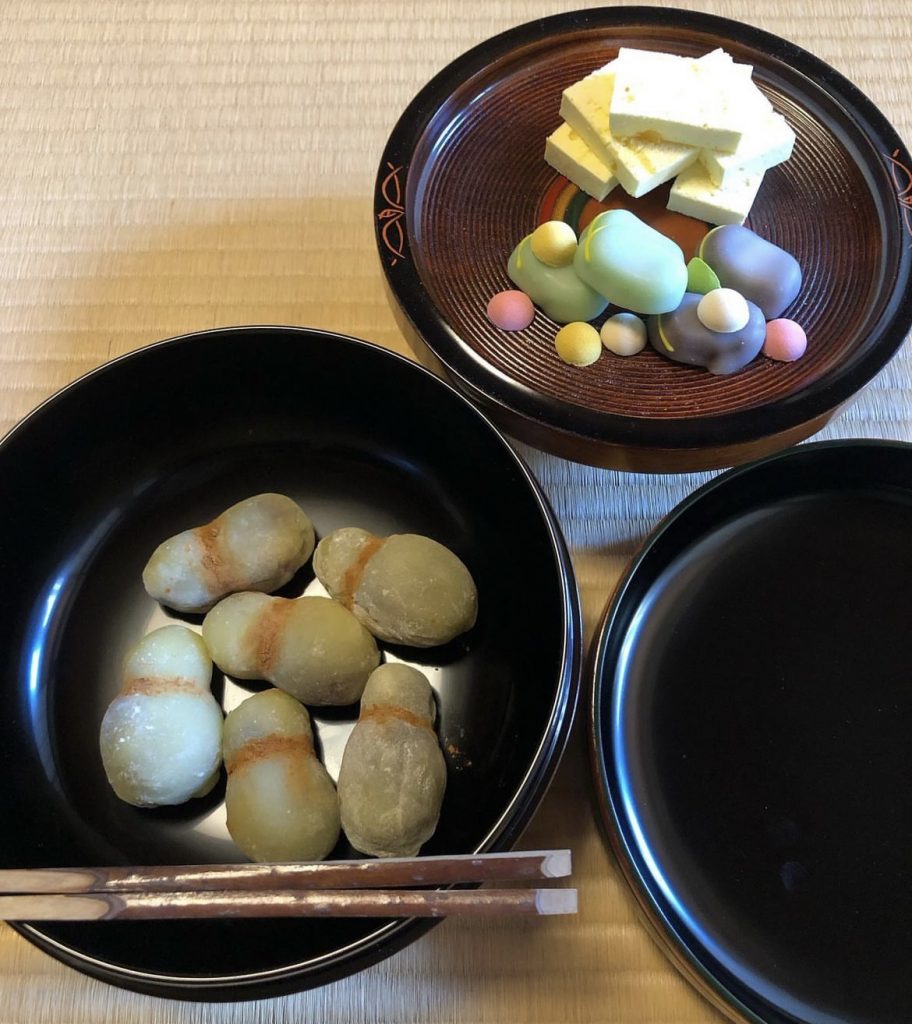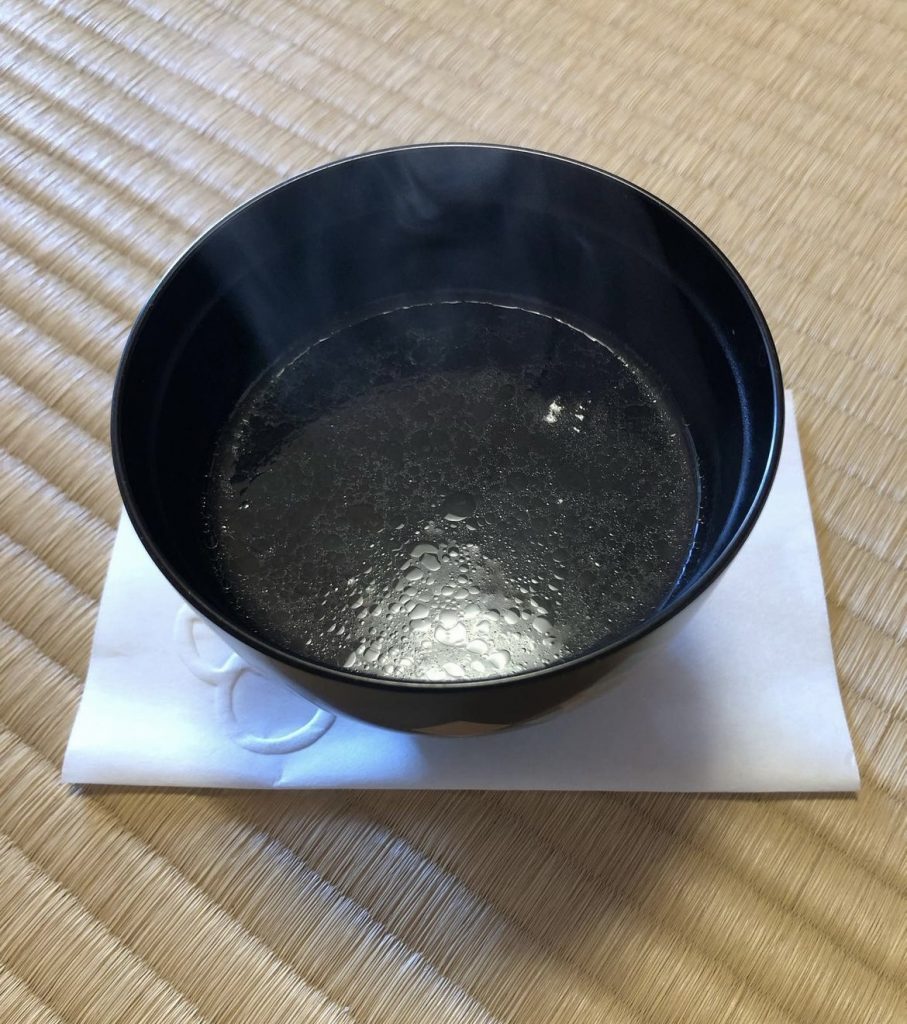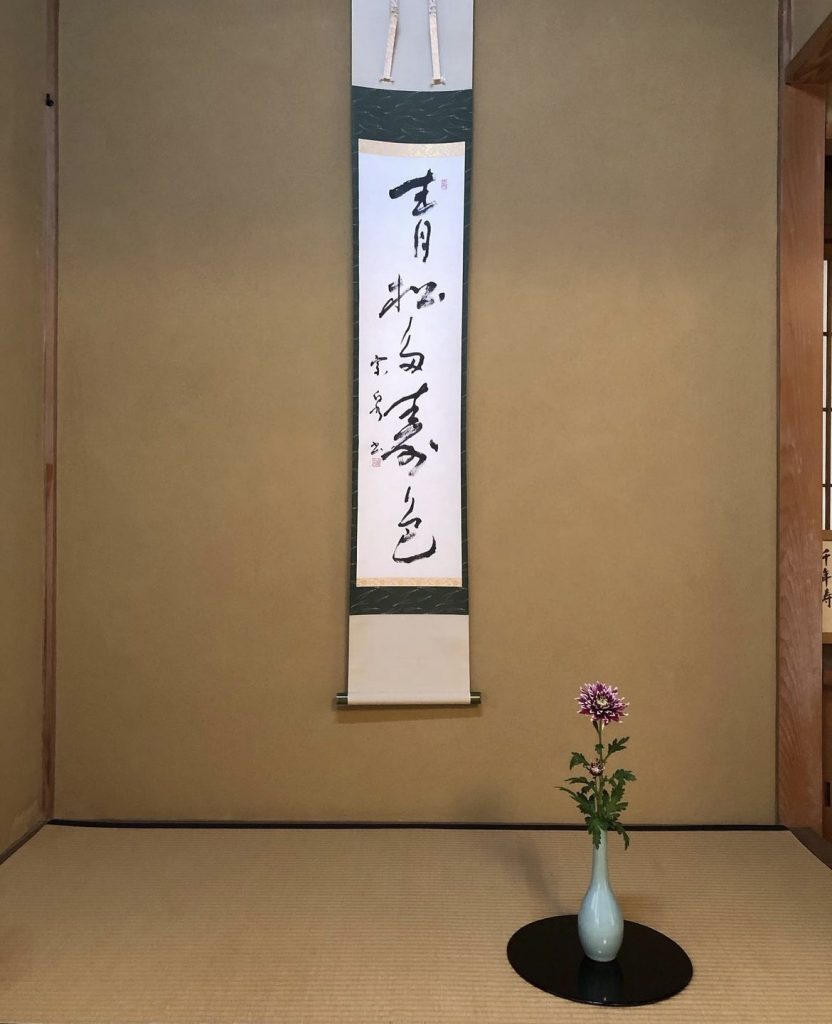令和6年3月2日のお稽古
3月 2024
 Closed
Closed月初はいつも軽い緊張と共に始まります。
そう、お道具が一新するのです。
でも大丈夫、今月はきっと糸巻棚。予習もばっちり無敵の私。
すっかり油断したところに目に飛び込む先生作の大口水指。
そうきたか!
茶室に鎮座する、その圧倒的な存在感に衝撃が走ります。
動揺を隠しつつお床の前に進み、1年ぶりにお目もじの若いご夫婦にご挨拶。
春らしい水仙にようやく心が落ち着いてきました。
螺鈿細工の箱を干菓子器とする先生のセンスに感心し。
さあお楽しみ、先生お手製の今日の主菓子は。
見た目もどっしりとした蓬の串団子が、ツヤツヤといかにも美味しそうです。
えごま入り小豆餡?芋餡かも?
期待と共に頬張ると、本日1番の衝撃が! な、なんと 干し柿餡!!
・・・予想をはるかに超えた先生の発想に完敗です。
今月もまた、楽しいお稽古になりそうです。 (宗仁)




Filed under: 今月のお道具